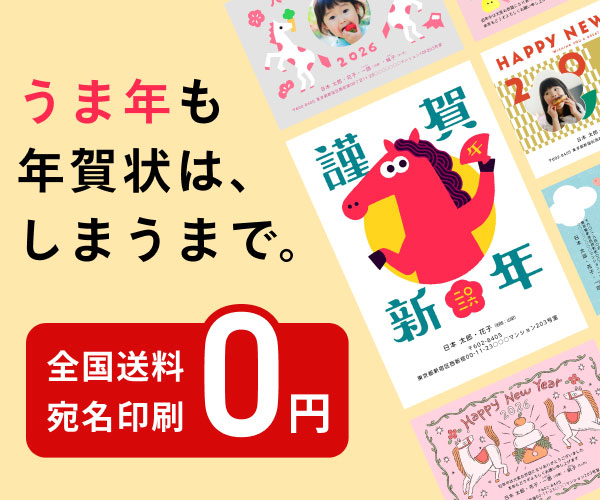喪中に年賀状は送れる?送る範囲や時期など役立つマナーを徹底解説
3親等(曾祖父母、叔父叔母など)やそれ以外の親族は喪中の対象外とされていますが、個人の判断で喪に服す場合もあります。
同居していたかどうかや生前の関係性を考慮し、個人の判断で喪に服すことも増えています。相手との関係性を考慮し、適切に対応しましょう。
親族に不幸があると、年末に年賀状を出してよいかどうか迷う方も多いのではないでしょうか。
日本では、個人を偲んで祝い事などを自粛し、別れた悲しみから立ち直るために喪中の期間を設け、年賀の欠礼を伝える喪中はがきを送る慣習があります。
喪中の範囲や喪中はがきを送るタイミングなど、一般常識として知っておくと、いざという時に安心です。 今回は、喪中の際の年賀状のマナーについて詳しく解説します。

喪中とは
喪中とは、近親者が亡くなった際に遺族・親族が故人を偲ぶ期間のことです。「喪」には身近な方や親しい方の死を悲しみ、冥福を祈りながら身を慎むという意味があり、この期間には「喪に服す」ことが求められます。
喪中の間は、お正月料理や年賀状、初詣などの正月行事をはじめ、慶事や派手な行動も控えるのが一般的です。
喪中の範囲
一般的には「亡くなった方から見て2親等以内の親族」が喪中の対象とされています。
・1親等:父母、配偶者、子
・2親等:祖父母、兄弟姉妹、孫
たとえば、自分の父母や配偶者の父母(義父母)は1親等または2親等にあたるため、義両親が亡くなった場合も喪中とするのが一般的です。一方、曾祖父母や叔父叔母、伯父伯母などは3親等に当たるため、喪中の範囲に含みません。
ただし、最近では「同居していたかどうか」や「生前の関係性の深さ」などを考慮し、形式にとらわれず、「故人とあまり関わりがなかったため喪中にしない」「心の整理のため一定期間慎む」など、個人の判断で喪に服す方も増えています。
喪中の期間
喪中の期間は、故人との続柄や関係性によって異なりますが、一般的には3か月~約1年間とされています。続柄ごとに見てみると、父母や義父母の場合は12~13か月、子どもの場合は3〜12か月、祖父母や兄弟姉妹などの2親等は1〜6か月とされています。
喪中と忌中の違い
喪中と似たような言葉として忌中があります。忌中とは、故人が亡くなって49日までの期間のことです。
「忌」の期間は、故人に祈りをささげるために身を慎み、外部との接触を避けます。忌明けは、仏教上では四十九日の法要後、神道では五十日祭を執り行った後とされています。
喪中の期間に控えるべきこと
喪中の期間は、故人を偲び、慎ましく過ごすことが求められるため、祝い事や華やかな行動は控えるのが一般的です。
例えば、年賀状のやりとりや新年のご挨拶、初詣、正月飾りやおせち料理といった正月行事は避けることとされています。また、結婚式などのお祝いごとへの参加や、自身の結婚・入籍、新築物件の購入やリフォームなども避けるのが望ましいとされます。
ただし、近年では個人や家庭の考え方によって柔軟に対応するケースも増えています。周囲への配慮を大切にしながら、自分なりの形で故人を偲ぶことが大切と言えるでしょう。
喪中はがき(年賀欠礼挨拶状)とは
喪中の期間中は、お正月行事をはじめとしたお祝いごとを控えるのが一般的です。年賀状もそのひとつで、近親者に不幸があった場合には、新年の挨拶を遠慮する旨を伝える「喪中はがき(年賀欠礼状)」を出すのがマナーとされています。
喪中はがきを出す目的は、「身内に不幸があったため、新年のご挨拶をご遠慮申し上げます」という気持ちを、相手へ丁寧に伝えることです。相手が年賀状の準備をする前に届くよう、早めの準備が必要です。
喪中はがきは誰に出す?
喪中はがきは前述した通り「身内に不幸があったため、新年の挨拶は控えさせていただきます」と相手に伝えるための欠礼状です。
喪中はがきを送る範囲は、送る相手と故人との関係や、疎遠になっているかどうかなどで決まりますが、基本となるのは「年賀状のやりとりをしている人」「葬儀に参列していただいた人」です。
本来、年賀状のやりとりをしている場合は、仕事関係者にも喪中はがきを出します。しかし最近では、プライベートで接点のない仕事関係者には、喪中はがきを送らず、通常通り年賀状を送るケースもあるようです。故人との関わりや間柄によって判断すべきなので、家族と相談の上決定すると良いでしょう。
喪中はがきは、あくまで「喪中につき、新年の挨拶は控えます」という趣旨を相手に知らせるためのもので、年賀状のやりとりがない人に送る必要はありません。ただし、故人がお世話になっていた場合や、訃報を知らせるべき相手には喪中はがきを出しても良いでしょう。
葬儀に参列していた人には喪中はがきを送らなくても良いと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、喪中はがきは訃報を知らせるためではなく、新年の挨拶は控えるということを相手に知らせるもののため、葬儀に参列していただいた方々にもきちんと送るのがマナーです。
ただし、お互い喪中である親族の場合は喪中はがきは省略しても良いとされています。
喪中はがきはいつ出す?
喪中はがきは、相手が年賀状を準備する前に届くように出すのがマナーです。一般的には11月中旬から12月初旬までに投函するのが適切とされています。年賀状の受付は毎年12月15日から始まるため、遅くとも12月中旬までには相手の手元に届くようにしましょう。
喪中はがきは、届くのが早すぎると相手が年賀状を書く頃に忘れてしまう可能性があります。相手が年賀状を準備し始めるタイミングを見計らって送ることが大切です。
喪中はがきは、事前に余裕を持って準備するのは難しい場合が多いかもしれませんが、送る範囲などを事前に話し合っておくと安心です。やむを得ず喪中はがきの準備が間に合わなかった場合は、年明けに寒中見舞いを送ると良いでしょう。
年末近くに不幸があったら?
年末に身内の不幸があった場合は、喪中はがきは送らないほうが賢明でしょう。12月に入ると先方がすでに年賀状を投函している可能性があるため、相手に気遣いをさせてしまうことになります。
喪中はがきを出す代わりに、年明けに寒中見舞いを送り、その中で年末に身内の不幸があったことを伝えるのがよいでしょう。
喪中見舞いとは
喪中見舞いとは、身内に不幸があった方に対して、お悔やみと励ましの気持ちを伝えるために送るお便りです。年賀状を控える喪中の方へ、年始の挨拶を避けつつも、相手を思いやる気持ちを丁寧に伝える手段として用いられます。
喪中見舞いを送る時期に決まりはなく、寒中見舞いよりも早くお悔やみを伝えたいという気遣いから始まっているため、喪中はがきを受け取ったらすぐに送ってよいとされています。
文面には、故人への哀悼の意や相手の心情を思いやる言葉を述べつつ、「寒さが厳しくなりますのでご自愛ください」などの気遣いの一言を添えるとよいでしょう。
寒中見舞いとは
寒中見舞いとは、寒さが厳しい時期に、相手の健康を気遣って送る季節の挨拶状です。一般的には松の内(1月7日頃)を過ぎた1月8日から、立春(2月4日頃)までの間に出します。
喪中の際には年賀状を控えるのがマナーとされていますが、寒中見舞いであれば新年の挨拶や感謝の気持ちを伝えられます。また、喪中の方に年賀状を送る代わりとしても適しており、お悔やみの言葉とともに、変わらぬ関係を大切にしたいという思いを表現できます。
寒中見舞いは、年賀状を出しそびれた場合や、返礼が遅れてしまった際にも使えるのが特徴です。
喪中はがきの基本マナー
喪中はがきにも押さえておくべきマナーがあります。あらためて喪中はがきの基本的なマナーやルールを確認しておきましょう。
喪中はがきの構成
喪中はがきは一般的に「5つの要素」で構成されます。
(1)喪中につき年賀欠礼の挨拶
(2)故人の名前・亡くなった月・享年、差出人から見た続柄
(3)送り相手への感謝の言葉
(4)結びの挨拶
(5)日付、差出人の住所・氏名
喪中はがきは縦書きが基本です。儀礼的な挨拶状には行頭は下げず、句読点は不要という慣習があるため、改行やスペースを活用すると良いでしょう。
故人の年齢は基本的には数え年で表記します。数え年は、生まれた時点で1歳とし、1月1日の元旦を迎えるたびに1歳ずつ増えていく数え方です。ただし近年は数え年にこだわらず、満年齢で表記する方もいます。
故人の続柄は差出人から見た続柄で記載しましょう。夫婦連名で喪中はがきを出す場合は、夫から見た故人の続柄にします。差出人は夫、妻の順に記載し、子どもの名前は記載しません。
喪中はがきの文例
ここからは、喪中はがきの文例を2つご紹介します。
喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます
本年○月○日に○○(続柄)○○(故人の名前)が○○歳で永眠いたしました
生前に賜りましたご厚情に心から御礼申し上げますとともに
明年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます
令和○年○月
(差出人の住所・氏名)
喪中のため新年のご挨拶は失礼させていただきます
本年○月○日に○○(続柄)○○(故人の名前)が○○歳にて永眠いたしました
平素のご芳情を厚くお礼申し上げます
明年も変わらぬご厚誼をお願い申し上げます
令和○年○月
(差出人の住所・氏名)
喪中はがきの作成方法
喪中はがきの作成方法は、主に3つあります。
(1)郵便局で通常はがきを購入して弔事用切手を貼る
(2)市販の私製はがきを購入して弔事用切手を貼る
(3)ネット印刷サービスや店舗で注文する
以前販売されていた弔事用はがきが廃止されたため、現在は無地の「通常はがき」または私製はがきを使用し、別途弔事用切手を貼る必要があります。弔事用切手は、全国の郵便局の窓口で購入可能です。
自宅で喪中はがきを印刷する場合は、私製はがきに弔事用切手を貼って投函しましょう。ネット印刷サービスであれば、文面やデザインを選ぶだけで簡単に注文できます。ご自身の状況やお気持ちに合わせて、無理のない方法を選ぶことが大切です。
高品質で安いネットプリント専門店「しまうまプリント」では、喪中はがきの印刷も可能です。
詳細・お申込みは喪中はがきページをご覧ください。
喪中はがきを作成する際の注意点
喪中はがきを作成する際は、文面やデザインにも気を配ることが大切です。
下記の5つのポイントを押さえておきましょう
(1)「拝啓」などの前文や時候の挨拶は省略する
(2)行頭の1字下げはしない
(3)句読点は使わない
(4)できるだけ縦書きで、数字は漢数字にする
(5)お祝い事や近況報告など、弔事以外の話題は避ける
デザインは白黒が一般的ですが、最近では落ち着いた色合いで故人を偲ぶスタイルも増えています。華美なデザインでなければ、ご家族や故人にゆかりのあるモチーフを取り入れても良いでしょう。
文字の色は薄墨または黒が使われますが、どちらで書いても失礼にはあたりません。ただし、宛名面には黒を使うのがマナーのため注意しましょう。
自分が喪中の場合
自分が喪中の場合は、年賀状の送付を控えるのがマナーです。代わりに喪中はがきを出して、年賀状を出せない旨を日頃お付き合いのある方に伝えましょう。
しかし、中には事情を知らずに年賀状を送ってくる方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、自分が喪中の期間に年賀状を受け取った場合の適切な対処法についてご紹介します。
喪中に年賀状を受け取った場合
喪中はがきを出すのが遅れてしまった場合や、年末に身内が亡くなってしまった場合、喪中に年賀状が届いてしまうこともあるかもしれません。また、相手が事情を知らずに年賀状を送ってしまうこともあるでしょう。
喪中に年賀状を受け取った場合は、松の内を過ぎてから「寒中見舞い」として返すのがマナーです。年賀状を受け取ったまま放置してしまうと、相手に失礼になる可能性があるため、寒中見舞いを出すようにしましょう。
寒中見舞いでは、喪中のため年始の挨拶を遠慮した旨や、年賀状をいただいたお礼を簡潔に伝えるのがポイントです。
相手が喪中の場合
相手が喪中の場合は、年賀状のやり取りには特に気を配る必要があります。相手から喪中はがきを受け取った際は、相手の気持ちを尊重しながら対応することが大切です。ここでは、相手が喪中の際にどのように対応すべきか、基本的なマナーや注意点をご紹介します。
喪中はがきが届いた場合
もし、相手から喪中はがきが届いた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。ここからは、喪中はがきを受け取った際の3つの対応法についてご紹介します。
返信しない
喪中はがきを受け取った場合、基本的に返信をしなくても良いとされています。一般的な手紙などには返事を出すのがマナーですが、喪中はがきの場合、故人やご遺族と年賀状のやり取りをする程度の関係であれば、返信しなくてもマナー違反にはあたりません。
故人やご遺族と親密な関係にあって、喪中はがきに返信したい場合は、年始状や寒中見舞いで挨拶しても良いでしょう。
年始状を送る
年始状とは「明けましておめでとうございます」や「迎春」など賀詞を使用しない年始の挨拶状です。おめでたい言葉の代わりに励ましの言葉などを添えることもあります。
年始状は、年賀状と同じく年始に届くよう送りましょう。ただし、年始状に年賀はがきを使用してはいけないため注意が必要です。
喪中見舞いまたは寒中見舞いを送る
喪中はがきが届いた場合は、相手を悼む気持ちを込めて、喪中見舞いや寒中見舞いを送るのが一般的です。喪中見舞いは相手の喪中期間中に送るお見舞いの挨拶状で、近年は喪中見舞いと一緒に線香などを送る方も増えています。
喪中見舞いを送るタイミングを逃してしまった場合は、松の内以降から立春までの期間に寒中見舞いを送ると良いでしょう。寒中見舞いは寒さが厳しい時期に相手の健康を気遣う挨拶状です。いずれの場合も、相手の気持ちを尊重し、丁寧な文面を心がけましょう。
喪中の方に年賀状を送ってしまった場合
喪中の相手にうっかり年賀状を送ってしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
相手が喪中であることを知らなかったり、年末に訃報があり喪中はがきが間に合わなかったりと、さまざまな状況が考えられます。
お詫びは必ずしも必要ではない
喪中はがきは「こちらから年賀状を出さないこと」を知らせるものであり、「年賀状を送らないでください」とお願いするものではありません。
そのため、年賀状を送ってしまったとしても、必ずしもお詫びをしなければならないというものではありません。
相手の気持ちに寄り添いたい場合は
とはいえ、相手の気持ちを思いやって何かしらのフォローをしたい場合は、寒中見舞いなどでさりげなくお悔やみや気遣いの言葉を伝えると良いでしょう。
「ご服喪中とは存じ上げず、年賀状を差し上げてしまい失礼いたしました」など、簡潔に気持ちを添えることで、丁寧な印象になります。
寒中見舞いは松の内(1月7日頃)を過ぎてから立春(2月4日頃)までに送ります。相手の状況に配慮し、控えめで穏やかな文面を心がけましょう。
まとめ
喪中は、故人のことを偲んで祝い事を自粛する期間で、法律などで強制されるものではありません。
昨今は、多様性が受け入れられる時代であり、「喪に服す」かどうかはその人の考え方にもよるでしょう。
とはいえ、年賀のマナーとして、喪中の期間に不快な思いを相手にさせないよう適切にふるまうことが求められます。
大切な人や関係の深かった人が亡くなった場合は、年賀状の代わりに送る喪中はがきの準備を早めに済ませ、故人との温かい思い出をゆっくり偲ぶ時間も作りましょう。
関連コンテンツ