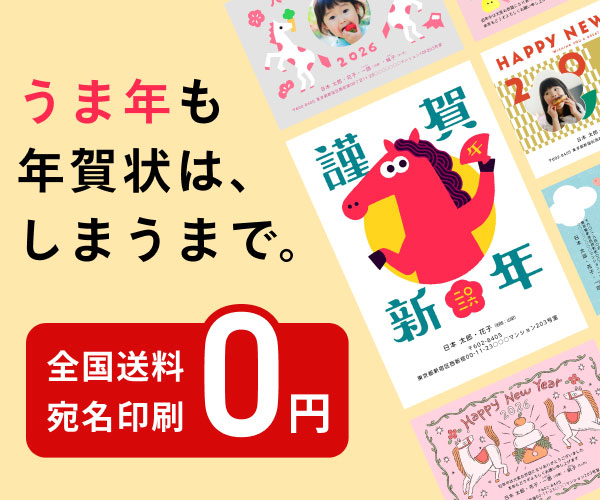日本のお正月とは?年末の準備や行事、食べ物の意味や由来についても解説
12月31日の大晦日には「年越しそば」を食べ、1年の厄を落とすとともに、翌年の健康を願います。お正月準備の仕上げに、想いを込めた年賀状を準備します。
元日には初詣に出かけ、1年の無事を祈願します。また、おせち料理やお雑煮を囲み、家族で新年を祝います。
これらの行事は、地域や家庭によって異なる場合もありますが、共通して「新年を清らかな気持ちで迎える」ことを大切にしています。
日本のお正月には、年賀状の他にも初詣や書き初め、鏡開きといった恒例行事が数多くあります。どれも慣れ親しんだ慣習ではありますが、それぞれが持つ意味や由来までは知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、お正月の基礎知識や年末の恒例行事、お正月料理などの意味や由来について解説します。正しい意味を知ることで、より充実した正月を過ごせるようになるでしょう。
「お正月」とは
お正月という言葉は、新年の最初のひと月、つまり1月のことを意味します。もともとは旧暦の1月を指していましたが、明治5年の改暦以降は新暦1月を指す言葉として使用されています。
お正月の「正」の字には、「あらためる」という意味があります。つまり、1年のはじまりである1月を「年をあらためる月」として、正月と呼ぶようになったとされています。
また、中国・秦の始皇帝の降誕月を「政月(セイグヮツ)」と呼んだことから、それが変化して「正月」となったという説もあります。
お正月の歴史
日本のお正月は、日本の年中行事の中でも最も古い行事です。詳しい起源や由来についてはわかっていませんが、仏教が日本に伝わった6世紀半ばよりも前からお正月は存在していたようです。
かつてのお正月は、現在のお盆のように先祖の霊を祀り、慰霊する行事でした。その後、五穀豊穣を司る年神様をお迎えし、その年の豊作を祈る行事となり、現在は新しい年をお祝いする行事として浸透しています。
年神様はどんな神様?
年神様は、元旦に各家を訪れ、豊穣や幸福をもたらすとともに、その家を一年通して見守ってくれる神様です。
年神様は、「正月様」「歳徳神(としとくじん)」「恵方神(えほうがみ)」など、地方によってさまざまな呼び名があります。
「年」は穀物や稲を意味する「とし」が語源であることから、年神様は稲の豊作をもたらす神様とする説や、災いから守ってくれる先祖の霊という説があります。どちらにしても、お正月には年神様を祀り、幸福を祈念する行事がお正月の中心行事です。
三が日とは
三が日(さんがにち)とは、新年を祝う特別な期間のことで、1月1日から3日までの3日間を指します。実際に祝日に定められているのは1月1日のみですが、3日間とも仕事や学校が休みになることが多く、正月らしい行事が行われるのが特徴です。
日本では一般的に、元日に初日の出を見たり初詣に行ったりしたあと、親族が集まっておせち料理を食べるなど、正月らしい行事を楽しみます。三が日は新しい年の無事と繁栄を祈り、新年を祝う大切な時間なのです。
松の内とは
松の内(まつのうち)とは、門松を飾って年神様をお迎えしている期間のことを言います。関東では一般的に元日から1月7日まで、関西では1月15日までと地域によって期間に差があります。
松の内が過ぎると門松やしめ縄などの正月飾りを片付け、地域によっては「どんど焼き」と呼ばれる行事でお焚き上げする風習が残っています。
また、寒中見舞いを出す場合は、松の内が明けてから立春までに届くように投函しましょう。
小正月とは
小正月(こしょうがつ)は1月15日または14日から16日にかけて行われる、正月行事の締めくくりです。かつては年が明けて最初の満月にあたる日を重視し、豊作祈願や厄払いの行事が各地で行われていました。
代表的な行事として「どんど焼き」があり、正月飾りや縁起物を燃やし、その煙とともに年神様を見送ります。
また、小豆粥を食べて邪気を払い、豊作や無病息災を祈る風習もあります。
お正月はいつからいつまで?
お正月というと、1月1日のみを指すと思っている方も多いかもしれません。本来「正月」は旧暦1月の別名で、広い意味では1月全体を指していました。
お正月の終わりを明確に区切る決まりはありませんが、門松やしめ飾りを片付ける松の内までを目安とするのが一般的です。ただし、関西のように松の内の1月15日までをお正月とするケースもあります。
「お正月は〇日まで」と言い切るのは難しいため、地域や慣習、考え方によってお正月の期間が異なると覚えておきましょう。
元旦と元日の違い
年賀状を書く際、何気なく「元旦」「元日」といった言葉を使う方も多いのではないでしょうか。元旦と元日、どちらも1月1日を表す言葉ですが、厳密には意味が異なります。
元旦は、1月1日の午前中を指す言葉です。つまり、1月1日の午後は元旦ではありません。一方、元日は1月1日の全日を指す言葉のため、どの時間帯にも使用できます。
1月1日に配達される年賀状は午前中に配達されることから、元旦を使用するのが一般的です。1月1日に届かない年賀状には、元旦と書かず、「令和◯年1月吉日」「新春吉日」といった言葉を選びましょう。
お正月を迎えるための準備
年末はクリスマスや忘年会など、12月はイベントが目白押しの季節です。同時に、12月はお正月を気持ちよく迎えるための準備期間でもあります。
お正月を迎えるための準備とは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、年末の代表的な慣習である「大掃除」と「年越し蕎麦」について解説します。
「年賀状」で大切な人に感謝を伝えよう
年賀状は、新年の挨拶とともに1年間の感謝を伝える大切な機会です。
昔は年始の挨拶をするため、相手の元に出向く慣習があり、遠方で直接挨拶ができない相手には、年始の挨拶を文書にして送っていました。これが、年賀状の始まりとされています。
郵便制度がはじまった明治20年頃には、年末年始の恒例行事として年賀状が定着しました。
近年ではSNSやメールでの挨拶も増えていますが、年賀状には手書きの温かみがあり、受け取る方の心に深く届きます。特に、日頃なかなか会えない友人や親戚との大切なコミュニケーションツールとして、近況報告や家族の様子を伝えることができます。
また、仕事でお世話になった方々への心からの感謝を表す機会としても最適です。
写真付きの年賀状や一筆添えた手書きのメッセージは、送り手の想いが伝わり、受け取った方との関係をより深めることができるでしょう。
年末年始の慌ただしい時期だからこそ、一枚一枚に感謝の気持ちを込めて、大切な方々とのつながりを大事にしていきたいものです。
年末の大掃除で新年を気持ちよく迎えよう
皆さんの多くは一年の汚れを落とし、清々しい気持ちで新年を迎えるために年末に大掃除をすると思います。毎年年末になると何気なくする方も多い大掃除ですが、これにも歴史と意味があるのをご存知でしょうか。
年末の恒例行事となっている大掃除の歴史は、平安時代まで遡ります。平安時代の宮中では、12月に1年間の煤を払う行事がありました。この行事は「煤払い(すすはらい)」と呼ばれ、大掃除の起源とされています。
大掃除は、自分のために行うのではなく、一年の間に溜まった汚れをとり、新年に各家を訪れる年神様を気持ちよく迎えるための行事です。
年末の慣習であるものの、二重の苦を連想させる12月29日や、年神様を迎え入れる12月31日に大掃除を行うことは、縁起が悪いとされています。
全国的な煤払いは12月13日に行われているため、大掃除も12月13日に行うのが正しい慣習といえるでしょう。
お正月飾りの準備を始めよう
お正月飾りの準備は、伝統的に大掃除と同じく12月13日以降に始めるのが良いとされています。これは、煤払いの日である12月13日に家の中を清めた後、清らかな状態で飾り付けを行うことで、年神様を迎える準備が整うとされているためです。
お正月飾りには、門松、しめ縄、鏡餅などがありますが、これらは年神様を迎えるための大切な目印となります。29日は「苦」に通じることから避け、余裕を持って28日までに飾り付けを済ませるのが理想的です。
早めに準備することで、年神様を丁寧にお迎えする心構えができ、新年を気持ちよく迎えることができます。また、年末年始の忙しい時期を少しでも余裕を持って過ごすためにも、計画的な準備を心がけましょう。
門松
門松とは、長さの異なる竹を束ねたものです。一年中落葉しない松と生命力の強い竹、そして新春に開花する梅と、3つの縁起物が用いられているのも門松の特徴です。
門松の起源は、平安時代の宮中儀礼「小松引き(こまつひき)」だと考えられています。「小松引き」とは、長寿祈願のために、正月初めの子の日に外出して小さな松の木を引き抜いてくる行事です。門松は、この「小松引き」が変遷して生まれたものとされています。
年神様が迷うことなく各家を訪れられるよう、目印として玄関や門の前に飾ります。
しめ縄
しめ縄とは、稲藁や麻を撚り合わせたもので、神聖な領域と現世を区分する結界の役割があります。
しめ縄の由来は、天照大神(アマテラスオオミカミ)が天の岩戸から出た際に、再び天の岩戸に入らないよう、しめ縄で戸を塞いだという日本神話です。「しめ」には神様の占める場所という意味があり、「しめ縄」の語源となっています。
しめ縄に縁起の良い飾りを付けたものを「しめ飾り」と呼び、お正月には玄関や神棚に飾るのが一般的です。
鏡餅
鏡餅とは、大小の丸いお餅2個を重ねたもので、年神様の魂が宿る場所として飾る、お正月飾りです。
鏡餅で使用する丸い餅の形は、かつて銅鏡と呼ばれていた丸い鏡に由来します。鏡は日の光を反射し、太陽のように光る鏡は、魂が宿るものと信じられてきました。また、お餅は神さまに捧げる神聖な食べ物だったことから、お餅を神様が宿る丸い鏡に見立て、お正月にお供えするようになったのです。
大小2段に重ねた鏡餅は、月と日、陰と陽を表し、「福徳が重なる」「円満に年を重ねる」などの意味が込められています。
鏡餅を飾る場所に決まりはありませんが、神棚や床の間、玄関に飾ると良いとされています。
年越し蕎麦で一年の締めくくりをしよう
年越し蕎麦とは、12月31日に縁起を担いで食べる蕎麦です。
由来には諸説ありますが、細く長い蕎麦にあやかって、長寿を祈願した説が有名です。
そのほかにも、蕎麦が切れやすいことから「厄災を断ち切る」や、飾り職人が金粉を集めるのに蕎麦粉を使っていたことから「金運が良くなるように」など、年越し蕎麦にはさまざまな願いが込められています。
年越しそばを食べる時間に決まりはありませんが、年をまたいで食べるのは良くないとされているため、大晦日に食べ終えましょう。
除夜の鐘を聞こう
除夜の鐘は、大晦日の深夜から元日にかけて寺院で鳴らされる鐘の音で、日本の年越しを象徴する伝統行事です。108回撞かれるのが一般的で、この回数は人間の煩悩の数を表すとされています。
鐘の音を聞くことで一年の穢れを祓い、新しい年を清らかな気持ちで迎えられると考えられています。一部の寺では参拝者が鐘を撞かせてもらえるため、大晦日の夜に家族や友人と寺に行くのも良いでしょう。
静寂の夜に響く鐘の音を聞きながら新年を迎える時間は、日本らしい厳かな風情に満ちています。
お正月の定番行事と楽しみ方
長い年月をかけて受け継がれてきたお正月行事にも、それぞれに深い意味が込められているのをご存じでしょうか。
ここからは、お正月に行われる「初日の出」「初詣」「書き初め」「正月遊び」「お年玉」といった行事について、なぜ行うのか、いつから行われているかなど解説します。
「初日の出」を見よう
初日の出は、元旦の早朝に現れる最初の日の出のことです。日本では、元日の朝に拝む初日の出は縁起が良く、一年の始まりを告げるおめでたい現象として古くから大切にされてきました。
新しい年の始まりに太陽を拝むことで、豊作や幸せを願う意味があり、元旦に天皇陛下が拝礼する「四方拝」にならって、庶民の間でも初日の出を拝むことが浸透していったとされています。
初日の出を迎える場所としては、山頂や海辺のほか、高層ビル、展望台などの高所が人気です。関東では犬吠埼や高尾山、関西では金剛山や六甲山などが初日の出の名所として知られています。
ご来光を浴びながら、年神様に今年の幸せを祈ることで、清々しい一年を迎えられるでしょう。
「初詣」で新年を気持ちよくスタートしよう
初詣とは、年が明けて初めて神社やお寺を参拝し、新年の無事や幸せを祈願する行事です。
初詣の起源は、平安時代から伝わる「年籠り(としごもり)」とされています。「年籠り」とは、大晦日の夕方から元旦にかけて、家長が氏神様のいる神社にこもって家内安全や豊作を夜通し祈るという慣習です。
「年籠り」は、「除夜詣」と「元日詣」に分かれ、この「元日詣」が現在の初詣と原型になったとされています。
初詣の期限はありませんが、昨年のお礼と新年の祈願をすることから、元日または三が日、遅くとも松の内までに参拝すると良いでしょう。
「おみくじ」で一年の運勢を占おう
おみくじは、神社・仏閣で吉凶を占うために引く「くじ」で、初詣の際には一年の運勢を占って多くの人がおみくじを引きます。
おみくじには吉凶の結果だけでなく、恋愛・学業・健康・仕事など生活に関わる具体的な指針や助言が書かれた「神様や仏様からのメッセージ」とされており、一年をどう過ごすかの参考にもなるでしょう。
結果に一喜一憂するのもお正月の醍醐味のひとつで、引いたおみくじは持ち帰ってお守りにする人もいれば、境内の木や専用の結び所に結んで「縁を結ぶ」人もいます。
ただし、おみくじは未来を決めるものではなく、自分の行動を正す指針として受け止めることが大切です。新しい年を前向きに過ごすために、ぜひ初詣で試してみましょう。
「書き初め」で新年の抱負や決意を表そう
書き初めとは、年が明けて初めて毛筆で字や絵を書く、日本の年中行事のひとつです。多くの方が子供の頃書き初めに挑戦した記憶があると思います。
一般的に、書き初めは1月2日に行います。1月2日は昔から仕事始めの日であったことから、今年の目標や抱負などを書く書き初めも、1月2日が良いとされています。
また、書道や茶道といったお稽古ごとは、1月2日から習い始めると上達するとされていることから、字の上達を願う意味も込められています。
書き初めで書く文字に決まりはありませんが、新年に向けての目標や抱負、「新春」や「初日の出」といった、お正月にふさわしい言葉などが定番です。
「正月遊び」で日本のお正月を楽しもう
日本には、お正月に古くから伝わる遊びを家族や友人と楽しむ風習があります。羽根つきやかるた、凧揚げやこま回しなどは、世代を超えて親しまれてきた日本の伝統的な遊びです。
家族や友人とともに正月ならではの楽しみに触れることで、新年の喜びをより深く味わえるでしょう。
羽根つき
羽根つきは、羽根に鳥の羽を付けた「羽根」を木製の羽子板で打ち合う遊びです。羽子板で羽根をつく際の音で邪気を払うとされたことから厄払いの意味も持っています。
古くは女の子の成長を願って羽子板が贈られる風習もあり、華やかな絵柄の羽子板は縁起物としても人気です。
できるだけ長く羽根を打ち合うことが良いとされ、羽根を落とした人は顔に罰として墨を塗られる風習がありますが、これは魔よけのおまじないとも言われています。
かるた
かるたは、読み札と絵札を使い、読み上げられた句に対応する絵札を素早く取る遊びです。正月の団らんで子どもから大人まで一緒に楽しめるため、世代を超えた交流の場にもなります。
代表的なのは「百人一首かるた」ですが、地域によってさまざまなかるたが存在し、遊びを通じて古典の和歌やその土地の文化に触れられるのも、かるたならではの魅力です。
集中力や瞬発力が求められるため、単なる娯楽にとどまらず知的な一面を持つ正月遊びとして広く親しまれています。
凧揚げ
凧揚げは、広い空に凧を舞い上げて楽しむ日本の伝統的な遊びです。かつては男の子の誕生や成長を祝う行事として行われており、天高く揚がる凧には子どもの健やかな成長を願う意味も込められていました。
複数の凧がつながった連凧や、相手の凧を落とす凧合戦など遊び方も豊富で、正月の風物詩として広場や河川敷などで楽しまれてきました。
凧のデザインも武者絵やキャラクターなど多彩で、冬の澄んだ空気の中で高く揚がる凧は新年の象徴的な光景と言えるでしょう。
駒
駒遊びは、木や金属で作られた駒を回して楽しむ正月遊びです。回した駒が長く安定して回り続ける様子は「物事が円滑に回る」「駒が回る音で邪気を払う」といった意味に通じ、縁起物とされてきました。
また、駒が一人で立って回ることから、うまく回せると子どもが早く独り立ちできるとも言われています。
紐を巻いて回す昔ながらの駒は少しコツがいりますが、上手に長く回せると新年を気持ちよく過ごせそうです。
「お年玉」で子どもたちに笑顔を届けよう
現代のお年玉は、主に大人から子どもへ贈られる新年のお祝い金として定着していますが、その起源は神様への供え物でした。
お年玉の語源である「御歳魂(おとしだま)」は、お正月に年神様を迎えるために供えられた丸餅のことを指します。この神聖な餅は、家長から家族へ分け与えられ、年神様の福を分かち合う大切な習わしでした。この餅玉は、各家庭でお雑煮として調理され、家族で食べることで一年の無病息災を願います。
江戸時代に入ると、商家が奉公人にお小遣いを与えたり、餅をつく代わりにお金を配ったりする慣習が生まれ、次第に現金を贈る現在の形へと変化していきました。お年玉は形を変えながらも、年神様の福を分け与えるという本来の意味を持ち続けています。
家族でゆっくり過ごそう
お正月は、一年の始まりを家族とともに過ごす大切な時間です。
普段は忙しくて顔を合わせる機会が少ない家庭でも、仕事や学校がお休みになる正月には食卓を囲みながらおせち料理を味わったり、初詣に出かけたりして、ゆったりとした時間を楽しめます。
また、親戚が集まり世代を超えた交流ができるのも正月ならではの魅力かもしれません。テレビを見たり正月遊びをしたり、家族団らんのひとときは新しい一年を笑顔でスタートさせる特別な時間になるでしょう。
お正月の定番食べ物
おせち料理やお雑煮など、お正月ならではの食べ物を楽しみにしている方も多いでしょう。お正月の食べ物には、縁起が良いとされるものが多く、年初めに食べるのにぴったりです。
ここでは、お正月の定番である食べ物の意味や由来について解説します。
お正月といえば「おせち料理」
お正月の代表的な食べ物と言うと、見た目にも華やかなおせち料理を思い浮かべる人も多いでしょう。
「おせち」は、神様にお供えした食べ物を「御節供(おせちく、おせつく)」と呼んでいたことに由来しています。元々は3月3日や5月5日などの節句の日に食べられていましたが、現在は一年の中で最もめでたい節句である、お正月に食べることが定着しました。
おせちには無病息災を意味する黒豆や子孫繁栄を願って食べられる数の子、不老長寿を意味する海老など、縁起の良い食材が使用されます。おせち料理には、「1年間健康で幸せに暮らせますように」という強い願いが込められているのです。また、重箱に詰めることにも「めでたいことを重ねる」という願いが込められています。
郷土性豊かな「お雑煮」
皆さんの家ではどのようなお雑煮を食べるでしょうか。丸餅のお雑煮、四角いお餅のお雑煮、味噌仕立てやすまし汁仕立てなど、それぞれの地域や家庭によって特徴があるのがお雑煮の面白さです。
お雑煮とは、お餅が入っている汁物を指し、色々な具材を煮合わせた「煮雑(にまぜ)」が語源とされています。
本来、お雑煮は年神様にお供えしていた食べ物を下げ、恩恵をいただくために食べられていた食べ物です。室町時代には、お雑煮は縁起の良い食べ物として宴の最初に食べることが定着し、現在はお正月の定番の食べ物になりました。
丸餅や角餅、白味噌仕立て、すまし汁仕立てなど、お雑煮の具材や味付けには地域差がありますが、必ず入っているのがお餅です。よく伸びるお餅には、長寿の願いが込められています。
お正月に飲む「お屠蘇(おとそ)」
お屠蘇とは、屠蘇散(とそさん)と呼ばれる5〜10酒類の生薬を日本酒やみりんで浸けこんだ、薬草酒の一種で、お正月に飲む祝い酒です。関東以北では日本酒をお屠蘇としてそのまま飲むこともあるようです。
お屠蘇の由来には「邪気を払い、魂を蘇らせる」という説や、「病気や災いをもたらす蘇を屠(ほふ)る」など諸説ありますが、どの説も悪い物を打ち負かし、長寿や無病息災を祈るという意味は共通しています。
その年の無病長寿を願うお屠蘇は、お正月がはじまる1月1日の朝、おせち料理やお雑煮などを食べる前に飲むのが良いとされています。また、三が日間に来客があった場合は、まずお屠蘇を振舞うことも礼儀です。
お正月を締めくくる行事
縁起の良い行事で始まったお正月は、縁起の良い行事で締めくくりたいですよね。
お正月を締めくくる行事として「鏡開き」や「どんど焼き」がありますが、これらの行事にも他の行事や慣習と同様、大切な意味が込められています。
めでたい気持ちと共に過ごしたお正月を気持ちよく締めくくるためにも、添えぞれの意味を再確認しておきましょう。
「鏡開き」で新年の恵みをいただこう
鏡開きとは、年神様の依り代として飾っていた鏡餅を下げ、割って食べる慣習です。松の内が明けた1月11日に行なうのが一般的ですが、松の内を15日とする地方では、15日または20日に行う場合もあります。
最近ではあらかじめ小分けにされた餅がパック詰めにされたものを買うため、鏡開きはしないという方も多いかもしれません。しかし、元々は硬くなった鏡餅を木槌で割るのが鏡開きでした。
鏡を開くことで、年神様をお見送りし、お正月に一区切りをつけます。開いた鏡餅を食べることで、年神様の恩恵をいただき、力を授かる意味もあります。
刃物は切腹を連想し、また神様に刃物をむけることは縁起が悪いとされるため、鏡開きでは刃物は使わず、手や木槌などを用いて叩き割りましょう。
「どんど焼き」で一年の無病息災を願おう
どんど焼きとは、松の内まで飾っていたお正月飾りや書き初め、昨年に授与した御札やお守りなどを、神社や地域の広場などに持ち寄って燃やす伝統的な火祭り行事です。
平安時代の宮中行事として行われていた、1月15日の夜に正月飾りや授与品をお焚き上げする「左義長」がどんど焼きの元とされており、地域によって「さえのかみ祭り」「左義長」「鬼火たき」「さいと焼き」「三九郎」などとも呼ばれています。
正月飾りを目印に家にきてくださった年神様を、燃やした煙とともに見送り、その年の無病息災や五穀豊穣、商売繁盛、家内安全を祈ります。
どんど焼きは、基本的に1月15日に行われる行事ですが、平日にあたる場合は日にちをずらす場合もあり、地域によってばらつきがあります。
「七草粥」で一年の健康を祈ろう
お正月の最終日、1月7日に食べる七草粥は、お正月のごちそうで弱った胃を休めるだけでなく、一年の健康を祈って食べる行事食のひとつです。
1月7日は、「人日(じんじつ)の節句」と呼ばれ、古代中国では7種類の野菜が入った汁物を食べて、無病息災を願う慣習でした。七草粥は、この「人日の節句」と、お正月に若菜を摘む日本の慣習「若菜摘み」が合わさって生まれた行事食だと考えられています。
一般的には、春の七草を入れたものが七草粥と呼ばれています。春の七草とは、芹(せり)、薺(なずな)、御形(ごぎょう)、繁縷(はこべら)、仏の座(ほとけのざ)、菘(すずな)、蘿蔔(すずしろ)の7種類です。
「寒中見舞い」を送ろう
寒中見舞いは、年賀状を出しそびれた相手や、喪中で新年の挨拶を控えている相手に対して送られる季節の便りです。
厳しい寒さの中でも体を大切にしてほしいという気持ちを伝える役割があり、松の内から立春の前日までに送るものとされています。
相手から年賀状をもらっていた場合は、年賀状のお礼とともに、新年の挨拶が遅れたお詫びを一文添えると良いでしょう。
相手が喪中の場合は賀詞やおめでたい言葉は避け、お悔やみの言葉を添えましょう。
近年ではメールやSNSで新年のご挨拶を済ませるケースも増えていますが、手書きのはがきで届けるとより温かみが伝わります。寒中見舞いは、疎遠になりがちな相手とのつながりを取り戻すきっかけにもなるでしょう。
寒中見舞いやその文例集については、以下の記事も参考にしてください。
自分が喪中のときに出す寒中見舞いのマナーや用途別の文例もご紹介!
お正月にやってはいけないこととは?
お正月には、新しい年の福を迎えるために避けるべきことがあるのはご存じでしょうか。代表的なのは掃除や洗濯で、お正月にこれらを行うと、せっかく招いた年神様を追い出してしまうとされ、縁起が良くないといわれています。
炊事場の火や水の使用を避けるのも伝統的な習わしで、保存のきくおせち料理にはそういった意味も込められています。また、煮焚きすると灰汁が出るため、「悪を出す」に通じることからも調理は避けるのがベターです。
そのほか、刃物の使用や喧嘩、散財なども、縁起を損なうと考えられています。
現代では全てを厳格に守る家庭は少なくなりましたが、昔ながらの風習を意識して静かに過ごすことで、気持ちを整え、穏やかに一年を始められるでしょう。
お正月準備の仕上げに、想いを込めた年賀状を
お正月飾りやおせち料理の準備と並んで、大切なのが年賀状の準備です。年神様をお迎えする準備と同様に、大切な人々との縁をつなぐ年賀状もまた、新年を迎えるための大切な準備のひとつです。
年末年始は慌ただしい時期だからこそ、1年間お世話になった方々への感謝の気持ちを込めて、丁寧に年賀状を作成したいものです。
写真入りの年賀状や手書きのメッセージを添えることで、より一層想いの伝わる年賀状になるでしょう。
お正月は、新しい年を迎えるとともに、人と人とのつながりを大切にする機会でもあります。年末準備のひとつとして、感謝の気持ちを込めた年賀状を送り、心豊かな新年を迎える準備を整えましょう。
まとめ
日本の伝統文化が息づくお正月の行事には、それぞれに深い意味が込められています。年神様をお迎えするための大掃除や飾り付け、一年の感謝を込めた年賀状、家族の健康と繁栄を願うおせち料理など、どれも大切な意味を持ちます。
年末年始は忙しく、すべてのお正月行事を行うことが難しい場合は、現代の生活に合った形で伝統文化を守る方法もひとつです。
おせち料理は一部を購入して手作りと組み合わせたり、大掃除は家族で分担して計画的に進めたりと、工夫してみましょう。年賀状作成にはしまうまプリントの「しまうま年賀状」です。スマートフォンひとつで、デザイン性の高い年賀状を作成でき、宛名印刷も無料で利用できます。
新年の挨拶と感謝の気持ちを込めた年賀状を送り、人とのつながりを感じられる心豊かなお正月を迎えましょう。