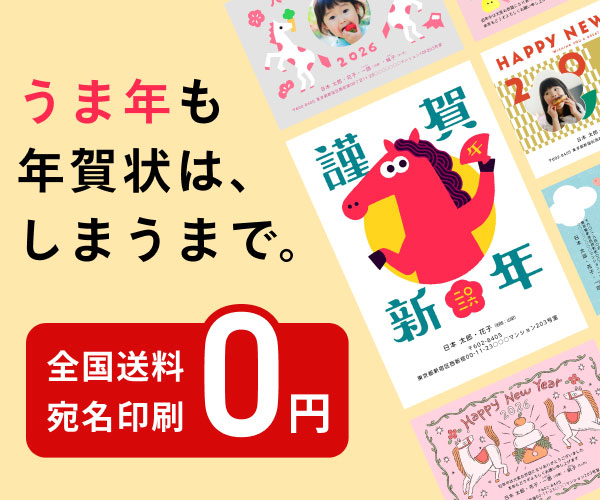2025年の干支「巳年」特集!知っておきたい豆知識や最新情報をお届け
午(うま)は、古くから人間とともに生きてきた動物で、健康や豊作を象徴するとされている動物です。中国の歴史文化においては、馬は「速さ」「活力」「自由」などを表しています。
そのため、丙午の年は「勢いとエネルギーに満ちて、活動的になる」年と考えられています。
2026年の干支は午(うま)で、60年に一度の丙午(ひのえうま)の年です。丙午は縁起が悪いと言われていますが、実際には迷信によるものが強いとされています。
この記事では、干支や午年、丙午について知っておきたい豆知識を紹介します。年賀状を準備する際のヒントとしてお役立てください。
そもそも干支とは
年末が近づくとよく耳にする「干支(えと)」という言葉。「干支」というと「子・丑・寅…」といった12種類の動物を思い浮かべる人が多いと思いますが、厳密にはそうではありません。
この章では「干支」について詳しく解説していきます。
「干支」とは「十干十二支」のこと
「干支」とは「十干十二支(じっかんじゅうにし)」を略した言葉です。聞きなれない言葉ですが、「十干十二支」とはいったい何でしょうか。
「十干」と「十二支」の説明は下記の通りです。
「十干」:甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸からなる10種類の要素のこと
「十二支」:子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥からなる12種類の動物のこと
「干支」とはこの「十干」と「十二支」を組み合わせた「十干十二支」のことです。
「十干」と「十二支」をそれぞれ組み合わせていくと、「甲子」「乙丑」「丙寅」…「癸亥」と全部で60の「干支」になります。
古代中国では、この「十干十二支」の組み合わせである60を周期にして、暦や時間、方位を表していました。その暦法上の用語としての「十干十二支」を短くしたものが、現在も「干支」として使われています。
十二支に関する縁起話
12種類の動物からなる十二支ですが、それぞれの動物に幸せを願う意味が込められています。各動物の特徴や習性になぞらえた縁起話についてご紹介します。
子:ネズミは繁殖力が高く「子宝」の象徴とされています。
丑:ウシは農耕の担い手であったことから「粘り強さ」「真面目さ」を表します。
寅:トラはその勇ましい印象から「決断力」や「才覚」を意味します。
卯:ウサギは温厚な性質から「家内安全」、また飛び跳ねることから「跳躍」「向上」をイメージさせます。
辰:タツは古くから中国では権力の象徴とされており、「正義」を表します。
巳:ヘビは脱皮を繰り返し成長することから、「生命力」や「再生」を連想させます。
午:古くから農耕などで活躍してきたウマは「豊作」や「健康」の意味が込められています。
未:ヒツジは群れで行動することから、「家内安全」や「平和」などを意味します。
申:サルはその賢さや器用さから、「臨機応変」を連想させます。
酉:トリはニワトリを指します。「取り込む」という言葉から「商売繁盛」の象徴とされてきました。
戌:主人に忠実であることから「忠義」や「安心」「勤勉」などを連想させます。
亥:イノシシの肉は万病に効くことから、「無病息災」を意味します。
海外にも干支はある?
西アジアや東ヨーロッパの一部の国では、日本同様、干支があります。しかし、日本とまったく同じというわけではありません。動物の種類が違う場合があります。
たとえば、タイやチベット、ベトナム、ベラルーシ、タイやトルコではウサギ年は猫年、イノシシ年は豚年です。また、モンゴルやトルコでは寅年は豹年です。
ちなみに、2026年は、多くの国が日本と同じように午年になります。
2026年の干支は午(うま)
2026年は、十二支の7番目にあたる午(うま)です。
馬は、農耕や運搬などだけでなく、武士の戦においても人々の生活で大きな役割を果たしていたことから、健康や豊作を象徴するとされている動物です。中国の歴史文化においては、馬は「速さ」「活力」「自由」などを表しています。情熱を持ってかなえたい夢を追いかけ、挑戦するために行動する時期として捉えられている年です。
一方で、「午」はもともと「忤」の漢字で「つきあたる」ことを意味しており、草木の成長が山場を迎え、衰える予兆が表れる時期を示しています。力強く勇ましいイメージの馬ですが、もともとの漢字の意味から、下り坂に向かう兆しもあるとされています。
午年は、成長が落ち着くタイミングであるため、日々の努力が実り、結果として報われる時期であるとも言える年です。目標に向かいながらも、少し立ち止まって気を休めるのによい一年なのかもしれません。
2026年は60年に一度の丙年(ひのえうま)でもある
2026年は、干支の60年周期のなかでも「丙午(ひのえうま)」にあたる年です。この章では、丙午は縁起が悪いと言われる理由や60年前の丙午で起こった出来事、出生率への影響について解説します。
丙午(ひのえうま)とは?
丙午は、十干の「丙」と十二支の「午」のどちらも火の性質があり、二重の意味を持つ年です。そのため、丙午の年は勢いとエネルギーに満ちあふれ、活動的になる年であると考えられています。
特徴としては、学びや努力が実を結び、一気に花開く勢いがある年です。一方で、場合によっては努力をしても結果が出ず、次の機会まで我慢し続けなければならない年になる可能性もあります。
努力し続けた結果が出るか出ないかは、自分次第なのかもしれません。
60年前の丙午に日本であった出来事は?
60年前の1966年(昭和41年)の丙午では、以下のような出来事がありました。
- 1966年2月4日:全日空ボーイング727型機が東京湾に墜落、133人全員死亡
- 1966年4月26日:公共交通機関(国鉄・私鉄)が全国一斉に戦後最大のストライキ実施
- 1966年6月25日:祝日法の改正が公布されたことにより、敬老の日・体育の日(現:スポーツの日、当時は10月10日)制定
- 1966年6月29日~7月3日:ビートルズ来日
- 1966年11月1日:国立劇場が開場
ファッションでは、ミニスカートやロングブーツが流行し、原宿族と呼ばれる独自のファッションを確立した若者が登場しました。音楽では、エレキギターに歌詞を乗せて歌うグループサウンズが人気を呼びます。
ほかにも、カラーテレビ、自動車、クーラーを総称した「新三種の神器」が流行語に選ばれるなど、新しいものであふれていました。1966年は、暗い出来事もありましたが、明るい話題にも恵まれた年であったと言えます。
丙午の年は縁起が悪いといわれるのはなぜ?
丙午の年は縁起が悪いといわれるのは、丙午は天災が多いという中国からの伝承と、「八百屋お七の話」による迷信によるものです。
中国から十干十二支が伝えられた際、丙午と丁巳の年は天災が多いとされていました。
江戸時代に、丙午生まれの娘・お七が恋人に会うために放火して火あぶりの刑にされた、「八百屋のお七」の話が広まったのも理由のひとつといわれています。
しかしながら、これらはあくまで迷信であり、根拠はありません。必ずしも縁起が悪いものととらえる必要はないため、安心してください。
丙午の年は出生率に影響する?
1966年は、迷信を信じた多くの夫婦が、丙午生まれになる妊娠・出産を避けたため、出生率が前年の18.6%から13.7%と大幅に減少しました。1906年も、丙午生まれの女性に対する偏見や差別を避けるべく、前後の年にずらして生年月日を申請した人が多かったようで、出生率は減少しています。
過去2回の丙午の年は出生率に影響しましたが、丙午に生まれることが悪いわけではありません。あえて妊娠・出産を避ける必要はなく、ご夫婦のタイミングで考えましょう。
知っておきたい午年の豆知識
午年には漢字や言い伝え、ことわざなど、知っておくとよい豆知識がたくさんあります。この章では、知っておきたい午年の豆知識を紹介します。
干支の午年はなぜ「馬」ではなく「午」の字を書くの?
「馬」を「午」と異なる字で書くのは、干支が年や時刻など時間の呼び名に由来するためです。
十二支は、もともと「年」を数えるための言葉として誕生しました。古代中国では、木星の位置を把握するために天を12に分け、それぞれ「子」から「亥」までの字を割り当てたことが始まりとされています。
割り当てた字に動物をあてはめたことで、人々に十二支が知られるようになり、別の字で広く認識され、異なる字で書かれるようになりました。
午(馬)の言い伝え
午(馬)は、縁起のよい動物とされています。なかでも馬の文字を左右逆にして書く「左馬」は、馬を逆から読むと「まう」となるため、おめでたい席での「舞い」を連想させる縁起物として知られています。
馬に左側から乗れば倒れないという言い伝えから、「左馬」は倒れないと言われ、人生が大きな問題なく平穏に過ごせるともいわれている言葉です。
馬は人が引くものですが、逆になった左馬は人を引いてくるという意味から、千客万来、商売繁盛などの開運にもよいとされています。
左馬の文字の下部分が巾着に似ているため、口がしっかり締まってお金が逃げないという意味で「巾着馬」とも呼ばれ、金運のお守りにも使用されるほどの縁起物です。
午(馬)に関することわざ
午(馬)に関連することわざは、たくさんあります。代表的なものをいくつか紹介します。
1.馬の耳に念仏
人の意見や忠告を言っても、まったく耳を貸さず効果がないことのたとえです。馬にありがたい念仏を聞かせてもまったく通じないことに由来します。
2.馬が合う
乗馬で騎手と馬の息がぴったり合う様子から、気が合い、意気投合することをいいます。
3.馬の耳に風/馬耳東風
他人の意見や忠告を聞かず、聞き流してしまうという意味です。馬は耳に風がふいても、何も感じないことに例えられています。
4.人間万事塞翁が馬
人生に起こることは予測不可能で移り変わり、良し悪しはすぐにわからないため、ささいなことで一喜一憂すべきではないというたとえです。塞翁の馬からつながった不幸と幸せを繰り返す故事に由来します。
5.馬子にも衣装
どんな人でも、身だしなみを整えれば立派に見えるということわざです。馬子は馬を引いて人や荷物を運ぶ職業で、身分が低くいつもみすぼらしい服を着ていましたが、きちんとした身なりをしたらそれなりに見えたことから来ています。
6.馬の骨
素性のしれない人のことをたとえています。中国で役に立たないものの象徴として、小さすぎる鶏の肋骨と、大きすぎて処分が難しい馬骨が挙げられたことが起源です。
7.じゃじゃ馬
人に慣れない暴れ馬のことをいい、扱いが難しい女性を指します。「じゃじゃ」は「嫌じゃ嫌じゃ」の略とされる説もありますが、やかましい虫の鳴き声や人の声を表す「じやじや」が変化した言葉とされています。そこから、人に慣れない馬がじゃじゃ馬と呼ばれるようになりました。
年賀状には午のイラストは必要?
年賀状には、必ずしも干支のイラストを入れる必要はありません。
しかしながら、干支はそれぞれのもつ縁起のよい特徴があるため、幸せを祈る意味で古くから年賀状によく使われています。お正月のあいさつでその年の干支を使うと、新年の始まりを再認識するきっかけにもなるため、年賀状にイラストを入れる人は多くいます。
干支以外にも、富士山や鏡餅、だるまなど、縁起物のイラストが入ったデザインも、年賀状の定番です。
イメージする年賀状のデザインにあわせて、必要であれば干支のイラストを入れるとよいでしょう。
しまうまプリントでは、その年の干支のイラストを使ったデザインはもちろん、縁起物のイラストが入ったデザインも取り扱っております。どちらも多数取りそろえておりますので、イメージに合うものをお探しください。
まとめ
午年で丙午である2026年は、迷信により縁起が悪いと言われる年です。しかしながら、60年前と違い、時代は進化し移り変わっています。迷信はあくまで迷信なので、むやみに信じる必要はありません。
来年の年賀状には、縁起物として午のイラストや午に関する言葉を添えて、明るい年にしていきましょう。
関連コンテンツ