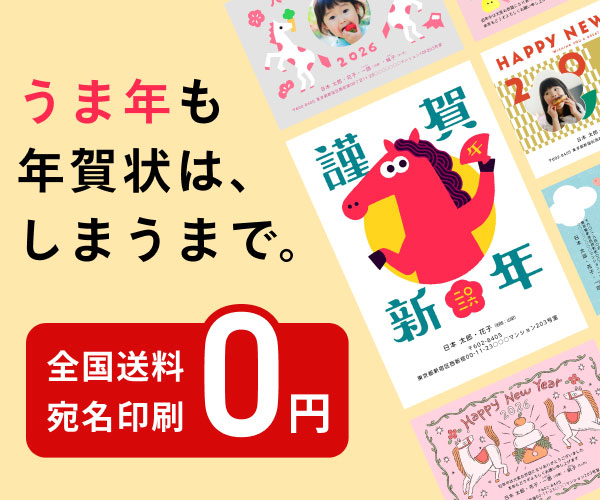【保存版】年賀状マナー早見表|宛名・賀詞・投函期限まで丸わかり!
宛名面では住所や氏名を正確に記載して敬称を適切に使用し、裏面では賀詞、謝辞、祈り、お願い、差出人情報の5つの要素を意識して相手に失礼のない文章にまとめましょう。
忌み言葉は使わない、句読点は使わない、書き損じた際は修正せず、新しい年賀はがきに書き直すといったことも大切です。
また、相手に合わせた年賀状を送ることも心がけましょう。
毎年年賀状を書いているものの、正しいルールやマナーはよく知らないという方も実は多いのではないでしょうか。せっかく時間をかけて年賀状を作成したのに、基本的なマナーを把握していないことで相手に良くない印象を持たれるのはもったいないことです。
今回は、年賀状の正しいマナーはもちろん、シーンに合わせた年賀状作成のポイントや注意点などをご紹介します。
「正しいマナーで年賀状を書きたい」「相手に失礼のない年賀状を作りたい」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
年賀状の基本的なマナー
年賀状は1年に一度、大切な方へ感謝の気持ちや近況を伝える大切なご挨拶です。しかし「これで失礼にならないかな?」とマナーに不安を感じる方も多いはず。
ここでは、年賀状を書くうえで最低限押さえておきたい基本マナーをわかりやすくご紹介します。
特に“宛名面の書き方”に関するルールを中心に解説しますので「失礼のない年賀状を送りたい」という方はぜひ確認しておきましょう。
表面(宛名面)のルールを守る
素敵なデザインの年賀状であっても、表面(宛名面)のルールが守られていないと失礼に当たるケースもあります。年賀状の表面はそれぞれの部分の書く場所に注意し、全体のバランスに気を付けるのがコツです。ここでは縦書きの年賀状のルールを説明します。
【住所】
郵便番号の一番右の枠下を基準に、住所を書き始めましょう。都道府県名やマンション名まで省略せず、正確に記入します。
番地や部屋番号の数字は、縦書きの場合「漢数字」を使用するのがマナーです。
また、ビジネスで送る場合には、会社名や部署名を省略せずに記載しましょう。
【名前】
郵便番号の大枠3桁の中心を目安に、大きめの文字でバランスよく名前を書きましょう。宛名が1人の場合はもちろん、夫婦・連名の場合でもそれぞれの名前の後に敬称をつけましょう。
【差出人】
表面に差出人の住所・名前を書く場合、左下の郵便番号の枠の幅に収まるように書きましょう。裏面に記載するなら表面に差出人の名前・住所は不要です。
【敬称・役職】
宛名に付ける敬称は相手によって使い分けます。
- 個人宛の場合:氏名の後に「様」を付ける
- 会社・団体宛の場合:氏名の代わりに「御中」を使用する(例:○○株式会社 御中)
目上の上司や恩師に送る場合は、氏名の上に役職名(部長、教授など)を記載し、その下に氏名+「様」を付けるとより丁寧な印象を与えられます。
【その他】
- 文字の色は基本的には黒を使用します。ポイントとして色を使用するのはOKです。
- 私製はがきを使用する際は、切手の下に朱色で「年賀」と書きましょう。
裏面(デザイン面)のフォーマットを守る
年賀状の裏面(デザイン面)は、相手に新年のご挨拶を伝える大切なスペースです。
この部分は「①賀詞」「②謝辞」「③祈り」「④お願い」「⑤日付・差出人情報」の5つの要素を意識して構成することで、読みやすく失礼のない年賀状に仕上がります。
それぞれの要素がどのような役割を持ち、どう書けばよいのかを解説します。
【①賀詞】
賀詞とは年賀状の冒頭に書く、新年を祝う言葉です。
例:「あけましておめでとうございます」「謹賀新年」「迎春」など
【②謝辞】
過去一年間のお礼や感謝の気持ちを伝える文章です。
例:「昨年中は大変お世話になりました」「旧年中はご支援いただき誠にありがとうございました」
ビジネスでもプライベートでも、相手に対する感謝をしっかり伝えることが大切です。
【③祈り】
相手の健康や幸福、会社であれば今後の繁栄を祈る一文を添えます。
例:「皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます」「貴社の益々のご発展をお祈りいたします」
相手の立場に合わせた祈りの言葉を選ぶことで、丁寧な印象を与えられます。
【④お願い】
今後の関係性やご支援をお願いする締めくくりの一文です。
例:「本年もどうぞよろしくお願い申し上げます」「今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます」
ビジネスシーンではより丁寧な表現が望まれます。
【⑤日付・差出人情報】
年賀状には新年の日付と、差出人情報を忘れずに記載しましょう。
例:「令和〇年 元旦」「20〇〇年1月1日」
また、表面(宛名面)に差出人情報を記載しない場合は、裏面に氏名や住所も記載する必要があります。
【その他】
相手に合わせて一言添えたメッセージを加えるとより心のこもった印象の良い年賀状になります。
正しい賀詞を用いる
賀詞にはさまざま種類があり、意味もそれぞれ違います。
年賀状を送る相手によって賀詞を使い分けましょう。
【相手を選ばないもの】
どの賀詞にしようか迷う場合は文章の賀詞を使いましょう。
「あけましておめでとうございます」
「謹んで新春のお慶びを申し上げます」
「新年おめでとうございます」
【親しい人向け】
仲の良い友達などにはカジュアルな文章の賀詞や英文もおすすめです。
「Happy New Year」
「あけましておめでとう」
【目下の人向け】
部下や後輩などには1文字または2文字の賀詞でも構いません。
「寿」(祝うこと 祝い)
「春」(正月 新春)
「迎春」(新春を迎えること)
「賀正」(新年を祝うこと)
【目上の人向け】
目上の方には敬意を払うために4文字もしくは文章の賀詞を使いましょう。
「謹賀新年」(謹んで新年のお祝いを申し上げます)
「恭賀新年」(恭しく新年のお祝いを申し上げます)
「初春のお慶びを申し上げます」
「謹んで新春の寿ぎを申し上げます」
また、「あけましておめでとうございます」「謹賀新年」「迎春」など、新年を祝う言葉(賀詞)はたくさんありますが、これらの言葉を重複させるのは間違った使い方です。デザインにすでに賀詞が入っているのに 、メッセージやスタンプでも賀詞を使ってしまう例はよく見かけるため、気を付けましょう。
元旦に届くように年賀状のスケジュールを立てる
年賀状は1月1日に届くように送るのがベストです。できれば元旦から1月3日の三が日までに届くように送りましょう。12月25日までに投函すれば元旦には相手に届くので、余裕をもって年賀状を作成しましょう。
また、通常はがきを使う場合、うっかり朱色で「年賀」を書かずに投函した場合、年内に配達されてしまうので注意が必要です。
松の内である1月7日(地域差あり)以内に届けば失礼にはあたりませんが、それ以降は寒中見舞いになります。
年賀状の返礼はできるだけ早く出す
年賀状を送っていなかった方から年賀状が届いた場合、できるだけ早くお返しの年賀状を作成し、投函するのが良いでしょう。なぜなら、一般的に年賀状として出す時期は、松の内である1月7日までとなっているからです。
年賀状を受け取ったものの送るのを忘れていたなどで、年賀状の返礼をやめようと考える方もいるかもしれません。
しかし、年賀状を返さないほうが失礼にあたります。
もし、旅行や家庭の都合などで「松の内」を超えてしまう場合は「寒中見舞い」に代えてはがきを送りましょう。その場合、遅れたお詫びの文章も一言添えるとベストです。
喪中だった場合は喪中はがきを出す
自分が喪中だった場合、年賀状を出さないのがマナーです。代わりに、年賀状の辞退をお伝えする「喪中はがき(年賀状欠礼状)」を出しましょう。喪中はがきは11月中、遅くても12月初め頃までを目安に、相手が年賀状の準備を始める前までには出すようにします。
喪中はがきは、「年賀状を送らないでください」という意味ではありません。相手から年賀状が届いた場合は、松の内を過ぎた後に寒中見舞いで返事をしましょう。喪中はがきを出していない相手から年賀状が届いた場合には、年賀状をいただいたお礼と併せて、喪中であったことを添えるようにしましょう。
喪中はがきの詳細については、以下の記事もご覧ください。
喪中に年賀状は送れる?送る範囲や時期など役立つマナーを徹底解説
ポジティブな内容にまとめる
年賀状は1年に1度、お世話になった方々に日頃の感謝の気持ちや、近況を伝えるために送るものです。年が明けてすぐ目にするので、受け取った人が楽しい気持ちになれるようポジティブな内容にまとめると印象も良くなります。
年賀状のマナー違反・注意すべき点
年賀状を作成するにあたって注意すべき点がいくつかあります。気づかないうちに、マナー違反になっている年賀状もあるかもしれません。特に目上の方や会社の上司に年賀状を出す場合は、失礼にあたらないよう気を付ける必要があります。
「実はこんなことがマナー違反だったとは…!」と後から知って焦らないよう、注意点を把握しておきましょう。
忌み言葉は使わない
年賀状は元旦というお祝い事(慶事)に送るものです。不幸や別れを連想させる「忌み言葉」は縁起が悪いため、使わないのがマナーです。ここでは、年賀状で避けるべき忌み言葉と、その理由について紹介します。
忌み言葉の例
- 去年:「去」という字は「別れる・離れる」を意味するため、「旧年」「昨年」と言い換える
- 病む:病気や健康不安を連想させるためNG
- 枯れる:花や木が枯れる様子が不吉とされるためNG
- 終わる:終焉や関係の終わりを連想させるためNG
- 滅びる:繁栄とは逆の意味を持つためNG
- 禍(コロナ禍など):「禍」は災いを意味し、不幸を連想させるため避ける
忌み言葉を避けることで、新年にふさわしい前向きで明るい印象の年賀状に仕上がります。
句読点は使わない
年賀状に「、」や「。」といった句読点は使わないようにしましょう。普段、文章の区切りや文章を読みやすくするために句読点を使用しますが、一般的には年賀状といった相手に敬意を払った文章には使用しません。
句読点を使うことで、お祝い事に区切りをつけるということで縁起が良くないと考えられているためだといわれています。もし、文章が長くなったり、読みづらいと感じるのであれば、改行やスペースをうまく活用しましょう。
修正ペンや二重線は使わない
手書きやプリンターで印刷した後に誤字・脱字を見つけてしまうこともあるでしょう。「1か所だけだから…」とついついその箇所だけ修正ペンや二重線などで修正したくなりますが、それはマナー違反となります。
「書き直しが面倒だから…」と名前間違いや住所間違いをそのままにして送るのは、相手に大変失礼です。書き損じた年賀状は、所定の手数料を払えば郵便局で交換してもらえるため、新しい年賀状を使用して書き直しましょう。
年賀状の書き損じを無駄にしない!ケース別の交換・活用方法を紹介
取引先・上司には縦書きが基本
年賀状の書式は縦書き・横書きどちらでもマナー違反にはなりません。
しかし、取引先や上司といった目上の方に送る場合は「縦書き」が基本とされています。日本語は本来縦書きが正式な形であり、フォーマルな印象を与えるためです。
通信面(裏面)のデザインによっては横書きの方が読みやすい場合もありますが、その場合は宛名面(表面)も横書きに揃えるのがルールです。
ただし、ビジネスで送る年賀状や親戚など目上の方に対しては、デザインよりも礼儀を優先し、縦書きで統一するのが無難です。
写真入り年賀状は送る相手で使い分けが必要
スマートフォンなどで子どもやペットの写真が手軽に撮りやすくなりました。近況報告も兼ねて、写真入り年賀状を送る場合も多いでしょう。しかし、写真を使用した年賀状を送る場合は、相手によって配慮が必要です。
写真入り年賀状は、あくまでプライベートなものです。友人や親戚など、親しい間柄であれば、問題ありません。
家族ぐるみで付き合いがない限り、上司や取引先など、仕事関係の方に送る場合は、写真入り年賀状は控えるのがベターです。ビジネスなどで年賀状を使用する際は、別のデザインを用意するなど、TPO(時間・場所・場面)に合わせて年賀状を使い分けると良いでしょう。
送る相手に合わせた年賀状作成のコツ
年賀状とは新年の挨拶だけではなく、出産や結婚など自分のライフステージの変化などを相手に伝えるいい機会です。ここではプライベートなことからビジネスまで、送る相手に合わせた年賀状作成のコツをご紹介します。
家族・親族への年賀状
家族や親族には、温かみのある親しみやすいデザインや手書きのメッセージを添えると喜ばれます。
近況報告として、出産・結婚・引越しなどライフイベントを写真付きで知らせるのもおすすめです。カジュアルすぎない程度に、親しみのこもった言葉遣いを心がけましょう。
友人・親しい知人への年賀状
友人や親しい知人には、堅苦しさを抑えたカジュアルなデザインや文面でも問題ありません。昨年の思い出話や「今年も一緒に○○しよう!」といった一言メッセージを添えると、より気持ちが伝わります。
ただし、久しぶりに連絡を取る相手には最低限の丁寧さを意識しましょう。
目上の人・上司・恩師への年賀状
目上の方には、フォーマルな縦書きのデザインを選び、敬意を示す丁寧な言葉遣いが必要です。
プライベートな話題は控えめにし「旧年中は大変お世話になりました」「本年もご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます」といった定型的な表現で、感謝とお願いの気持ちをしっかり伝えましょう。
文末には相手の健康やご活躍を祈る一文も忘れずに。
取引先・ビジネス相手への年賀状
取引先やビジネス関係者には、会社としての信頼感を与えるフォーマルなデザインを選びます。縦書きが基本で、宛名面・裏面ともに失礼のない表現を心がけましょう。
「旧年中は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます」などビジネスにふさわしい表現を用い、「貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます」といった祈りの言葉を添えます。
担当者個人宛でも敬称や役職を正確に記載するのがマナーです。
以下の記事も参考にしてください。
取引先に送るビジネス年賀状のマナーとは?書き方のポイントも解説
結婚や出産報告を兼ねる場合
結婚報告
写真入りデザインがおすすめ。二人の素敵な笑顔の写真で新年のスタートを報告しましょう。式に参列いただいた方にはお礼の言葉を添えるといいですね。
また、送る相手によってデザインを選んでみるのもいいです。目上の方や職場関係の方にはフォーマルタイプが、親しいご友人やご親戚にはカジュアルタイプがおすすめです。
出産報告
写真入りデザインがおすすめ。赤ちゃんの顔を撮った写真、家族で撮った写真で赤ちゃんとお母さんの無事を報告してみましょう。メッセージに赤ちゃんの近況報告を入れてみるのもいいですね。
ただし、出産はデリケートな話題でもあり、送る相手によってデザインの使い分けをするなどの配慮も大切です。
年賀状デザインのポイント
しまうまプリントでは、送る相手やシーンに合わせた20種類以上のデザインカテゴリをご用意しています。
取引先や上司にはフォーマルな和風デザイン、友人や親しい方にはカジュアルなデザインが好印象です。
さらに、手書きで一言メッセージを添えたり、写真やシールでデコレーションすることで、オリジナル感のある特別な一枚に仕上がります。
デジタル派に伝えたい!紙の年賀状の良さとは?
デジタルツールの発達により、新年の挨拶をメールやSNSで送るという方も増えています。手軽に送れたり、住所を聞かなくても送れたりするなど便利なツールではありますが、紙の年賀状にはデジタルツールにはない魅力があります。
元旦にポストを開けた時のワクワク感や1枚1枚読み進める楽しさ、手書きの温かさなど、相手から届く年賀状から、より人とのつながりを感じられるはずです。丁寧に作られた年賀状からは、相手のこだわりも感じ取れるでしょう。
受け取るだけではなく、自分で作って送る楽しさも年賀状の醍醐味です。家族写真や子どもの写真を添えて送る方もいるでしょう。昔の年賀状を取っておくことで、家族の思い出や子どもの成長を振り返ることができ、懐かしさも感じられます。
年賀状を作ることが億劫になったり、年賀状をやめたい気持ちになったりしている方は、今一度、年賀状の良さを再確認してみませんか。
まとめ
毎年、年賀状を作成しているにも関わらず、実は知らなかったマナーやルールがあったかもしれません。最低限のマナーやポイントをしっかり把握しておくと安心ですね。あくまでもマナーは、敬意や感謝を正しく伝えるためのものであるため、心を込めて年賀状を作成するのが大前提です。
年賀状は送る人によってこだわりのポイントが違うため、受け取る側も毎年楽しみにしていることでしょう。マナーも細かく、1枚1枚用意するのは大変ですが、気持ちのこもった年賀状は相手の心にも響きます。直前になってあれこれ不安にならないよう、年賀状のマナーやルールをしっかりと把握しておきましょう。
関連コンテンツ
よくあるご質問
好印象を抱かせる年賀状作成のコツを教えてください
結婚・出産報告では写真入りのデザインがおすすめ。
上司や目上の人に年賀状を出す場合は、カジュアルすぎないものがよいでしょう。
近況報告などひと言メッセージを手書きで入れたり、マスキングテープやシールなどでデコレーションすると、より温かみを感じてもらえる年賀状になります。
使わないほうがよいNGワードはどんなものがありますか?
「あけましておめでとうございます」「謹賀新年」「迎春」など、新年を祝う言葉(賀詞)はたくさんありますが、これらの言葉を重複させるのは間違った使い方です。
デザインにすでに賀詞が入っているのに 、メッセージやスタンプでも賀詞を使ってしまう例はよく見かけるので気を付けましょう。